・葉の色が濃い方が良い野菜だと思ったら大間違い
2つのチンゲンサイの葉っぱの色を見比べてみます。葉っぱの色が薄いのと濃いものとがあります。これは何が違うかというと、葉っぱに含まれる窒素の量が違うんですね。どちらが本物かというと、実は葉っぱの色が薄い方です。皆さんは多分誤解していると思うのですが、葉色の濃いほうが葉緑素が多くて、栄養価も高い、良い野菜と思われがちなんですね。ところがそれは大きな間違いです。
土壌の中に肥料分の窒素がたくさん入って、作物が過剰に窒素を吸収すると、葉っぱの色はどんどん濃くなっていきます。この濃い緑色の野菜は茹でると色落ちしてしまいます。茹で汁の中に色がでてきます。それは葉緑素ではないのです。葉緑素の色というのは、本来はそんなに濃い緑色をしているわけでは決してないのです。葉緑素以外のいろんな色素が混ざって、濃い緑色になっているわけです。
色の薄い方は茹でたら緑色がもっと鮮やかになります。もっときれいになります。そして茹で汁のなかに色はあまりでてきません。ちゃんと育った理想的な野菜の色というのは、5月の新緑の色というふうに考えていただきたいと思います。あんなに薄い色でほんとうにいいのか、栄養が足りないんじゃないか、と思われる方が多いと思うのですが、はるかにこちらの方が栄養価は高いし、おいしいです。しっかり健康に野菜が育つということは、その中に含まれているビタミンとかいろいろな栄養成分がしっかり入っているということです。
本物の野菜というはの、葉っぱの色が薄くて、なおかつ艶があること。そうして、葉がしなっとせずにしっかりしていて、包丁で刻んでも「刃応え」があり、シャキッ、ザクッと、バッサリ切れます。葉の色が薄くても、艶がなく、しなっとしていて薄っぺらい腰の弱い野菜とはぜんぜん違いますよ。
それでは、なぜ作物は窒素を過剰に吸収すると不健康になるのでしょうか。少し難しい話になりますが、根から吸収した窒素をアミノ酸やタンパク質にするのに、余分なエネルギーをつかってしまうからなのです。せっかく葉を太陽に向けて、一生懸命に光合成(※1)をして太陽エネルギーを蓄えても、それを窒素の同化につかってしまうと、作物全体の維持に必要なエネルギーが不足してしまったり、肝心な養分、たとえばビタミン群などの合成もままなりません。収量を上げたり、大きくするために窒素をバンバンやった野菜は、図体がでかいだけで中身はあまり栄養がないということです。
(※1)光合成<こうごうせい> … 緑色植物がエネルギーを用いて、大気中から取り込んだ炭酸ガスを固定(有機物に転化)する過程をいう。そのときに水が消費され、固定された炭酸ガスとほぼ同量の酸素を大気中に排出する。
その点が有機栽培と慣行栽培の、つまり土が健康であるかないかの違いになってでてくるわけです。窒素の栄養素が腹八分目で育った有機栽培の野菜は小さくても中身の栄養価は確実にしっかりあるんだ、と思っていただいたらいいと思います。それが本当の育ち方なのです。
・白菜の黒いポツポツは、窒素過剰の印
ところで白菜の白いところに、ポツポツと小さな一ミリにも満たない黒点が付いているのを見たことはありませんか。それは適正な窒素よりも多い、過剰な窒素が土壌に与えられて、白菜の中の窒素分が多くなったときに出てくる現象です。苦味やエグ味が出てきます。
・本物の野菜は対称性があって見た目にも美しい … 葉っぱの形を見る
葉の付け根から葉の先のてっぺんまで通っている太い葉脈を主脈といいます。この主脈に沿って下から左右に次々と葉脈が均等に分かれていっているのが、正しい育ち方をした証拠で、主脈を折り目にして、左右を重ねてみると、左右対称形になるというのが作物の本来の姿なのです。
養分と水の通り道であるこの葉脈が、右・左・右・左と順になってでていればいいのですが、どれかが抜け落ちていて、右・右・左・右というふうになっていたり、クニャっと曲がっていたりすると、それはその葉が生長していくときに、根に何らかの障害が起こっていたことを意味します。また、葉っぱの左右どちらかが幅が広かったりするのは、養分のやり過ぎで、あるとき途中でぐっと生長したのではないかと思います。このように葉っぱを見ただけでも生育の仕方の履歴がわかるわけです。
・本物の野菜は対称性があって見た目にも美しい … 葉序を見る
作物が育って、葉が一枚ずつ出てゆくときの角度と順序は、作物それぞれに固有のものがあって、ちゃんと決まっているのです。これを葉序といいます。対称性について、これを見るのがもうひとつのポイントです。
葉序を見るときのコツは、根の方を手前にして軸を見るのです。こうすると、どういう順序でどのくらいの角度で葉っぱがついているかというのがわかります。
キャベツだったら、葉っぱが5枚出て、6枚目でようやく最初の位置にくるわけです。それまでに2回転するのです。だから360度を2倍して、それを5で割ったら144度くらいになるのです。で、健康に育った正常なキャベツだと、葉と葉の角度がほぼ144度くらいで、葉が順番に展開していくわけです。そういう意味でしっかりちゃんと育った野菜というのは、必ず対称性があって、見た目にも美しいのです。
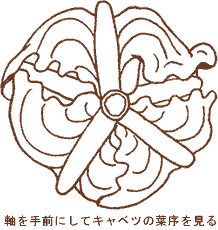
・葉っぱを並べるときれいな放物線を描く
いちばん外側に付いている古い葉っぱから最後の小さな葉っぱまで順にバラバラに外して、それを葉柄の下端をそろえてから左から右へと一直線に並べてみます。するとだんだん葉の背丈が高くなってゆき、左側から3分の1くらいのところで葉っぱがいちばん大きくなって長くなり、その後はだんだん背丈が低くなってゆくはずです。この山のような輪郭を放物線といいますが、滑らかな放物線になるのが、理想的な作物の育ち方なのです。つまり健康で丈夫に育った命あふれる野菜の第一条件なのです。これは葉物類だけでなく、ダイコンやカブの葉にも当てはまることです。
さて、順に並べてもきれいな放物線を描かず、デコボコがある野菜は問題です。生育途中のある時期に過剰な養分が投与されると、その時だけ普通の生育速度よりも素早く生育することになり、その部分の葉だけが異常に大きく、背丈も高くなってしまうのです。異常に生長した部分が結局、二つ目の山になったり、山が一つであつても頂上付近が平坦になったりして、放物線が描けないのです。また根が傷つけられたりすると、その部分の葉だけが極端に短くなったりします。
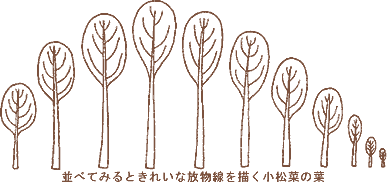
・維管束<いかんそく>の大きさがそろっていてしかも等間隔に並んでいる … 結球野菜の軸と葉物の茎の断面を見る
キャベツや白菜などの結球野菜の軸と切断面をよく観察すると、緑に近いところに、黄色みを帯びた小さな丸が緑色に沿って並んで一周しているのが見えます。この丸は、維管束といいますが、光合成でできた糖分がエネルギー源として葉から根にむかって降りてゆき、根から吸収された養分と水は地上部にむかって移動してゆく、細かいチューブなのです。
維管束は、人間でいうと血管に相当する重要な器官ですから、しっかりと丈夫につくられていなければなりません。しっかりと健康に育った結球野菜では、維管束の大きさがそろっていて、しかも軸のふちに等間隔で均一にきれいな円周を描いています。もし、大きさがそろっていなかったり、等間隔で並んでいない場合は、まともに育った結球野菜とはいえません。
こういうことが個々の野菜について全部いえるわけです。葉物の場合はどこで見分けたらいいのかというと、根と茎の際を切ると、その断面に維管束が緑の点となって並んでいるのが見えるはずです。結球野菜同様に、その大きさが違っていたり、等間隔に並んでなかったりすれば、それはまともな育ち方をしていないということです。
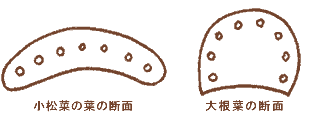 |
